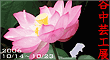2006年10月26日 (木)
丸井金猊『南天絵圖』
1932(昭和7)年に描かれた『南天絵圖』は、サイズ W725×H1,200mmで、絹本に着彩・軸の仕様。保存状態は前回紹介した『鷺圖 (仮)』よりはマシな環境といえるだろうか? 一応は桐の絵具箪笥の下段抽斗の中に絹本を丸めた状態にして包装紙で包んで収められていた。タイトル・年数情報はその包装紙に祖父がペン字で書き記していたものによる。表装は昔から何かとお世話になっている三鷹の飛高堂にお願いした。
1932年というと祖父が東京美術学校の日本画科を卒業する前年にあたり、学内の課題として描いていた可能性も高い。そう思って同期の花である杉山寧氏のアーカイヴを調べてみたところ、『南天図』という作品を1929(昭和4)年に描かれていることがわかった(鎌倉大谷記念美術館蔵)。しかし、3年早く描かれている上に葉の色付き方もまるで違う。学内の課題で描いたと早急に結論づけるのはちょっと難しそうだ。
 右の画像が『南天絵圖』の表具を除いた全体像を複写したもので、丸井金猊リソースの中でもとりわけ描写の細密度が高いものであることは画像をクリックしてこちらにアクセスすれば、実物をご覧になられたことのない方でもある程度は理解できるはずだ。実際、この時期の動植物を中心とした静物画を、コンセプチュアルな画題を求めた活動期後半(といっても20代後半だけど)の大作よりも好まれる方は意外と多い。それは画のリアリティをどこに求めるかによっても違ってくるのだろう。
右の画像が『南天絵圖』の表具を除いた全体像を複写したもので、丸井金猊リソースの中でもとりわけ描写の細密度が高いものであることは画像をクリックしてこちらにアクセスすれば、実物をご覧になられたことのない方でもある程度は理解できるはずだ。実際、この時期の動植物を中心とした静物画を、コンセプチュアルな画題を求めた活動期後半(といっても20代後半だけど)の大作よりも好まれる方は意外と多い。それは画のリアリティをどこに求めるかによっても違ってくるのだろう。
私個人が興味深く見ているのは、冒頭で掲載した南天が実を付けた部分のディテールである。これもほとんど実物大となる Largeサイズ にして見てもらうとより一層わかりやすいだろうが、実の幾つかの塗料が剥離し、下塗りした明るい朱色が浮き出ててるように見える部分があることにお気づきいただけるだろうか? 私にはその塗料の剥離した調子がより一層南天の実をリアルに見せることに貢献しているように感じられるのだ。それは祖父が最初から剥離を想定して描いていたのか、それとも剥離したように敢えて見せかけて描いたのか(つまり剥離していないということになる)、そこのところはよくわからない。ただ、どうも out of control のボーダーラインをさまよう事象に心吸い寄せられがちになってしまうのは私の体質とでも言うしかない(汗)
ところで今回の展示では大作屏風『壁畫に集ふ』に、新しく出てきた『霜晨』『芥子花圖(仮)』、あとは常設状態になってる『鷺圖(仮)』を出すということが決まっていた以外は現場判断で展示物を決めようということになっていた。それで芸工展の行われている秋だからということで、季節に合わせて南天、百合、椎茸、西洋芙蓉といったモチーフの画が選ばれることになった。まあ、芸工展の行われる季節は毎年秋なので、毎回秋モノを選んでいたらすぐネタ切れになってしまうとも言えるのだが。。
ともあれ実家には三鷹金猊居から持ってきた南天の鉢が、2Fのバルコニーに置いてあり、展示期間中、まだ『南天絵圖』のような実までは付けなかったが、徐々に葉を色づかせ始めていた。いよいよ秋も本格的に深まっていきそうな気配だ。
【写真】2006.10.22 10:21, 谷中M類栖/2f バルコニーにて
【補遺】展示終了後に、祖父が遺した下絵を再確認していたら、この『南天絵圖』の下絵も出てきたのだが、驚いたことに上記の軸装した『南天絵圖』はその下絵の左半分で、実は鳥の描かれた右側半分があったことが判明したのだ(下絵画像参照)。以前に下絵もすべてチェックしたつもりでいたのに、すっかりその事実を忘れていた。こういうものはしっかり情報整理して書き残しておかないといけない。