2004年02月29日 (日)
現地ノイズ調査2
建方見学後、休憩がてらに先日母と豊田さんで行ったという和菓子の喜久屋に入り、現地ノイズ調査を再び実施。
古い和菓子屋なだけに大したサッシュを使ってるわけではないが、それでも開け閉めすると随分交通音は違う。エンジン吹かす音も確かにうるさいが、ハイスピードで走ってる車のタイヤがシューッと擦れる音が案外気になるものだ。あと、このお店では車が横を通過するたびに巻き起こる風でサッシュがガタンガタン音を立てるのが一番気になってしまった。そういう音はうちでは発生しないと思うんで、問題はないかと思うが。。
豊田さんが来られる前にセブンイレブンでもチェックしたり、向かいのマンションの6階住人にも話を聞いていたので、それらも合わせて報告し、まあ、ひとまず最初は標準の一枚ガラス+サッシュをエアタイト仕様で使うというので大丈夫なんじゃないか?、もしうるさく感じられるようなら後付で取り替えるという方向で話は落ち着いた。
 店を出る頃にはちょうどお昼時となっていたので、僕が蕎麦好きなのを知ってる豊田さんから、上棟式の日のお昼にも行く予定になってる「鷹匠」で食べませんか?と誘われ、もちろんOKってことで藍染通りを降りていくと、上棟式の晩に妻と宿泊予定にしている「澤の屋旅館」が出て来た。この旅館は如何にも谷中な話だが、外国人旅行者が好んで泊まる旅館らしく、Webサイトも手作り的ながら日英両対応。宿泊価格はシングル4700円、ツイン8800円と国内宿泊費として考えれば高くはないが、貧乏外国人旅行者からしたら簡単には泊まれない価格。ということは、つまりお客はそれなりにプチブルな人が多いのだろう。本当は日暮里の駅を降りてすぐのところにあるゲルマニウム温湯と謳われたちょっと怪しげな「寿々木旅館」ってところに泊まってみたかったのだが、妻もいるし危ないと母に言われ、豊田さんも推奨される「澤の屋」の方を選んだのである。個人的にはこういう場末の旅館って妙に心浮立つものがあるんだけどね。
店を出る頃にはちょうどお昼時となっていたので、僕が蕎麦好きなのを知ってる豊田さんから、上棟式の日のお昼にも行く予定になってる「鷹匠」で食べませんか?と誘われ、もちろんOKってことで藍染通りを降りていくと、上棟式の晩に妻と宿泊予定にしている「澤の屋旅館」が出て来た。この旅館は如何にも谷中な話だが、外国人旅行者が好んで泊まる旅館らしく、Webサイトも手作り的ながら日英両対応。宿泊価格はシングル4700円、ツイン8800円と国内宿泊費として考えれば高くはないが、貧乏外国人旅行者からしたら簡単には泊まれない価格。ということは、つまりお客はそれなりにプチブルな人が多いのだろう。本当は日暮里の駅を降りてすぐのところにあるゲルマニウム温湯と謳われたちょっと怪しげな「寿々木旅館」ってところに泊まってみたかったのだが、妻もいるし危ないと母に言われ、豊田さんも推奨される「澤の屋」の方を選んだのである。個人的にはこういう場末の旅館って妙に心浮立つものがあるんだけどね。
 さてしかし、肝心の「鷹匠」は開店はしていたものの、この日は貸し切り予約が入っていて入店できず。そこで豊田さんも行ったことないけど、近くに割と美味しいと言われてる讃岐饂飩の店「根の津」があるというので入ってみると、なんとそこでKちゃんがバイトしてました。ま、谷中に住んでるのは知ってたけど、まさかこんなところで会うとはね(^^;)
さてしかし、肝心の「鷹匠」は開店はしていたものの、この日は貸し切り予約が入っていて入店できず。そこで豊田さんも行ったことないけど、近くに割と美味しいと言われてる讃岐饂飩の店「根の津」があるというので入ってみると、なんとそこでKちゃんがバイトしてました。ま、谷中に住んでるのは知ってたけど、まさかこんなところで会うとはね(^^;)
店内では、最近この手の作りの建築が増えてる(俗にいう癒し空間?)といった四方山話。豊田さん曰くこの手のものを作ってるのは大抵自分たち世代(豊田さんは現在42歳)の建築家なんだとか。。純和風というわけではないけど、なんとなく各国テイストを適度に織り交ぜ、光を抑え気味にしたこぢんまりと落ち着く空間を造形する。こうした傾向が顕著になったのは自分たち世代から海外旅行が気軽にできるようになったのが大きな要因じゃないか?(※1)と豊田さんは言われていた。私もこの手の場所はたまに入ると確かに落ち着くんだけど、これが毎日となるとどうなんだろ?とも思う。それはおそらく自分が三鷹金猊居というある種、厳正に日本建築の伝統形式に沿った住居環境で暮らしてきたことと大きく関係するだろう。癒しや緩さよりも落ち着くものが緊張感の方にあるのだ。
建方見学 - 裏手にまわって
敷地の裏側をまわる前にそういえば敷地北西側にお住まいの永松さんご夫婦と会った。
地鎮祭時のご挨拶ではご不在だったので、改めて建築家が変わった旨を話して、豊田さんを紹介。といってもお隣の柏山さんとは親子関係なんで話はすでに行き渡っていた。
永松邸はうちの建物でほとんどが影に入ってしまうものの、好意的に完成を見まもってくれているようだ。ただ、現場付近に昼食後のものと思われるゴミが散らかってることを指摘されてしまい(^^;)、それに関しては豊田さんがしっかり伝えときますとのこと。
 さて裏側。
さて裏側。
柏山邸の横の細い路地を入って、まずは柏山邸と永松邸の間からどのように見えるかを確認。
続いて、浅見邸の駐車場からも見てみようとしたが、そこからは我々の背の高さでは何も見ることができなかった。
道をしばし奥に入っていくと途中からタラップにかかる屋根の部分だけが見えてくる。その後またしばらく見えなくなって、ぐるっとまわって法蔵院のあたりまで来るとちらっとタラップ屋根が見える。 しっかり見るには法蔵院の中のお墓のあるところまで行かないとって感じか? しかし、我々がタラップを上り下りしたり、滑車を使って荷物の上げ下げをしてる様子はおそらくそこからは丸見えで、案外お参りしてる人からは何やってるんだ!アレ?と気にならずにはいられなくなってしまう雰囲気かもしれない。そういえば墓場からは母の部屋の上部あたりまでが見えるということは母の部屋からも墓場は見えるということか?(^^;)
しっかり見るには法蔵院の中のお墓のあるところまで行かないとって感じか? しかし、我々がタラップを上り下りしたり、滑車を使って荷物の上げ下げをしてる様子はおそらくそこからは丸見えで、案外お参りしてる人からは何やってるんだ!アレ?と気にならずにはいられなくなってしまう雰囲気かもしれない。そういえば墓場からは母の部屋の上部あたりまでが見えるということは母の部屋からも墓場は見えるということか?(^^;)
 一乗寺の東側を抜け、今度は言問通り沿いのセブンイレブンやルネ上野桜木のある方へ。
一乗寺の東側を抜け、今度は言問通り沿いのセブンイレブンやルネ上野桜木のある方へ。
こちらからの見え具合は実質正面よりもこの角度から見た面がファサードと言いたくなるくらい全体像がよく見える。正面は言問通りが狭くて引いて見るというほどの距離が取れないし、言問通りの谷中六丁目交差点が若干折れているので、東からの視界が大きく開けているのだ。それは言い換えれば、うちの2階バルコニーや3階両親の部屋からの見晴らしが良いということを示してくれる。
しかし、こちらから見ても何よりも目立つのはタラップだ。本当にタラップで何かやってるとどこからも丸見えだと思って間違いない。とはいえ、このタラップのおかげで間違いなくファサードが無理なく表情を持ってくれたし、第一、豊田案以前の一乗寺の壁と平行して2、3階まで立ち上がる案になっていたとしたら、相当に重苦しい印象を与えてしまっただろう。豊田案の大胆さもさることながら、案外それをあっさり受け容れた我が家の判断力もこの件に関してのみはあながち捨てたもんじゃないなと思う。
まだ完全に確定していないサッシュの色の取り合いについても話し合う。
お寺側にシャイングレーのサッシュとその色に近い感じのガルバリウムの波板鋼板を組み合わせることは確定しているが、果たして正面を黒のサッシュにしてよいものなのかどうか? まずお寺側と正面でサッシュの色が違ってしまうことを豊田さんは気にしておられ、私はその場では言わなかったが黒サッシュとALCパネルの白吹付が武家屋敷のような雰囲気になってしまいはしないか?という心配が多少はある。無難なのはすべてをシャイングレーのサッシュにしてしまうことだろうが、その場合、シャイングレーが遠くから見て光に当たったときにどう見えるかが問題だ。シルバー系のように白く飛んでしまうと、最近小ざっぱり系若手建築家の間でありがちな如何にもな建築で終わってしまう。もちろん古き良き近代建築には白壁+黒サッシュの取り合わせは多く見られるが、今回の場合の黒の利用は若干挑戦といった意味合いが強くなるんじゃないか?(外したときが悲惨)と思う。
建方見学
夜行バスは予定通り新宿朝6時着。ひとまず歌舞伎町向かいのラーメン屋で腹拵えして、山手線をぐるっと外回りで今回初めて鶯谷下車で敷地まで歩いてみた。で、南口側から出てしまったんだが、どうやら北口の方が多少は近かったようだ。しかし、どっちにしたところで鶯谷で降りるなら、上野か日暮里から行った方がいい。直線距離では一番近いはずだが、かなり迂回しないとならないのよね。
 さて、すでに完了してしまった建方工事。
さて、すでに完了してしまった建方工事。
7:45頃に現地到着したが、やはり今日の工事はもうないようだ。今回バスで行くことにしたのも、工事が早朝から始まるので、前日三鷹に来ておいて翌朝谷中まで出向くよりも、到着した足でそのまま現場に向かった方が効率的且つ確実だと思われたからだ。しかし、その思いつきも虚しく終わってしまった。
ただ、工事中でなかったおかげで写真は撮りたいようにじっくり撮れたとも言える。昨夕、工事中に撮影した母は迷惑がられてる感じがあってなかなか思うように写真が撮れなかったそうだ。とはいえ、前日に来てれば両日にわたって撮ることもできたわけで、やっぱり大いに悔やまれることには変わりない。とまあ、しかし、恨み節もこの辺にしとこう(^^;)
 9:00ちょっと前に向かいのマンションの住人が出て来たので、非常階段をあがらせてくれないかお願いすると、前にも一度来られましたよね?とちょうど一年前の1月頃に声を掛けてあがらせてもらった6階の住人の若いお兄さんだった。これから出掛けるときだというのに、わざわざ6階まで付いてきてくれて大感謝!である(ま、心おきなく写真を撮るわけには行かなくなってしまったが)。騒音のことなども聞いてみる。6階なのでちょっと参考にはならないかもしれないが、夜間は交通量もそれほど多くなく、車の騒音で眠れないと感じたことは一度もないとのこと。ただ、今、うちがやってるのがまさにそうだけど、聞き慣れない工事音とかはやっぱりうるさく感じてしまうらしい。交通量の多い昼間は気にすればうるさいと感じるかもしれないけど、気にすること自体がほとんどないと、まあ、それは当たり前と言えば当たり前の話。あと、写真を撮って何かするんですか?と聞かれたので、Web で最近レポート始めた旨、伝えた。URL も教えておくんだったな。というか、名刺でも作ってみてもいいかもしれない。
9:00ちょっと前に向かいのマンションの住人が出て来たので、非常階段をあがらせてくれないかお願いすると、前にも一度来られましたよね?とちょうど一年前の1月頃に声を掛けてあがらせてもらった6階の住人の若いお兄さんだった。これから出掛けるときだというのに、わざわざ6階まで付いてきてくれて大感謝!である(ま、心おきなく写真を撮るわけには行かなくなってしまったが)。騒音のことなども聞いてみる。6階なのでちょっと参考にはならないかもしれないが、夜間は交通量もそれほど多くなく、車の騒音で眠れないと感じたことは一度もないとのこと。ただ、今、うちがやってるのがまさにそうだけど、聞き慣れない工事音とかはやっぱりうるさく感じてしまうらしい。交通量の多い昼間は気にすればうるさいと感じるかもしれないけど、気にすること自体がほとんどないと、まあ、それは当たり前と言えば当たり前の話。あと、写真を撮って何かするんですか?と聞かれたので、Web で最近レポート始めた旨、伝えた。URL も教えておくんだったな。というか、名刺でも作ってみてもいいかもしれない。
と、ここまでまったく書いてなかったが、私の方からは想像してたよりも遙かに建物の高さが低く(特に1階)、基礎レベルが両隣よりかなり低い設定になってる(※2)ことに気づくまでは、ひょっとして寸法間違っちゃったんじゃないか?と不安になってたってことを話したり、あとは柏山さん側の鉄骨柱の垂直線が微妙に右に傾き気味なんじゃないか?と話したり。
それに対しての豊田さんの返答はおそらく北西側の鉄骨柱とパース上で重なるので、そう錯覚して見えるのでは?とのこと。豊田さんの昨晩見た感想はむしろ思ってた以上に大きいなという印象だったようだ。確かに近寄ってみるとパーゴラの位置も意外に高くて、大きいといえば大きくも見える。これが道路を挟んで見てしまうと両隣との関係から急に丈が低いように見えてしまうわけであるが。。
 窓位置の重なり具合は、妹の部屋の西側窓とキッチン西側窓がだいぶ被ってしまった感じだ(これは当初のイメージではレベル差を考えてなかったので、重ならないと思っていた)。バスの窓は重ならない訳ではないが、上から見下ろすような感じなんで心配はなさそう。キッチン北側窓もちょうど面一つズレてくれた恰好だ。
窓位置の重なり具合は、妹の部屋の西側窓とキッチン西側窓がだいぶ被ってしまった感じだ(これは当初のイメージではレベル差を考えてなかったので、重ならないと思っていた)。バスの窓は重ならない訳ではないが、上から見下ろすような感じなんで心配はなさそう。キッチン北側窓もちょうど面一つズレてくれた恰好だ。
豊田さんの気になる点としては、床材基礎として使われる波板鉄板がすでに上に載せられてしまっていて、その荷重で仮止めした鉄骨が微妙にズレるんじゃないかと心配されていた。まあ、搬入がしづらいことからやむを得ない処置なのではあろうが。。
その後、周囲をぐるっとまわって背後からの見え方など話し合ったが、長くなってるので別稿に譲る。
2004年02月28日 (土)
建方終わってる?
 夕方、母からの電話を妻が受け、建方(※)、ほどんど終わっちゃってるよ!どうすんの?の報せ(汗)
夕方、母からの電話を妻が受け、建方(※)、ほどんど終わっちゃってるよ!どうすんの?の報せ(汗)
当初の予定では28日はほとんど搬入作業に終始し、29日に本チャン工事が行われるということだったのだが、道路事情が心配されたほど混まなかったのと、29日の天気が天気予報によるとよくないということから一気に28日のうちに片付けてしまうことになったらしい。
しかし、そりゃー、え?え?え?という話で、ひとまず豊田さんに電話を入れてみると、豊田さんもマジですか?って感じで驚きのご様子。というか、この日は谷中のコミュニティセンター横の広い空き地のゴミ拾い&凧揚げを近所の子供たちを集めてやられていて、緊急の事態が発生した場合のみ連絡をもらって現地に赴くということになっていたらしい。よって、工事が早く進むことには何ら問題はなく、早く終わった旨の連絡はその時点ではまだ豊田さんにも届いていなかった。
 う〜む、しかし、工事のなかでも一番見ていて面白いという建方を見逃してしまうとは超オマヌケ&ガビ〜ンである。夕方、電話をかけてきた母も「そんなもん見たってしょうがない」が口癖の父をなかなか振り切れず、しかし、得も言えぬ胸騒ぎがして隙をついてこっそり出掛けたらしい。しかし、到着時には3階天井の最後の梁が掛けられんとしていたところだったらしく、実質、鉄骨が1階から立ち上がっていく様子はまるで記録できず仕舞いで終わってしまった(泪)
う〜む、しかし、工事のなかでも一番見ていて面白いという建方を見逃してしまうとは超オマヌケ&ガビ〜ンである。夕方、電話をかけてきた母も「そんなもん見たってしょうがない」が口癖の父をなかなか振り切れず、しかし、得も言えぬ胸騒ぎがして隙をついてこっそり出掛けたらしい。しかし、到着時には3階天井の最後の梁が掛けられんとしていたところだったらしく、実質、鉄骨が1階から立ち上がっていく様子はまるで記録できず仕舞いで終わってしまった(泪)
今にして思えば、引越日程を一日早めておくべきだったと後悔することしきりだが、引越期日指定時には上棟式の日取りがもっと早くに見込まれていたのだからやむを得まい。それともう一つのオマヌケは建方に合わせて夜行バスのチケットを取ってしまってたことである。もう別に29日に絶対行かないとならないということでもなくなってしまったのである。引越直後の疲労に加え、まるで荷物も片付いてない状態で家を出るのは心苦しい限りだが、3/1(月)に父方の伯母が乳癌の手術を受けることになってしまったので、どっちにしても出掛ける必然はあったのである。
この日は鉄骨職人が上に3人、下に2人の5人、道路片側車線を使っているため、交通整理のガードマンが3人、それに監督として山本さんといった布陣だったようだ。
2004年02月27日 (金)
引越
突然ですが、引っ越しました。
といっても至って近所。ほとんど道路挟んではす向かいのようなところで電話番号も変わりません。
いずれ転居のお知らせメール送るつもりですが、事前に新連絡先を知りたい方はこちらまで。
ところで今回の引越、引越屋のトラックをさほど大きくないのにケチったりしたもんで、積みきれない荷物もたくさん残って、後から台車で何往復もするハメに陥ってしまいました(泪)
さすがに疲れた。つーか、あの三鷹金猊居から仮住居へ移ったときの悪夢が再び想起されたというか。
来るべき三鷹仮住居→谷中引越時のために、今回の反省点を二三、メモっておこう。
1)見積もりを取りに来てもらう際に、できることなら配布される段ボールを持って来てもらう。それが無理なら最低でもサイズを聞いておく。段ボール箱ってホンマにピンからキリまであります。取っ手穴のあるのないの、紙質の頑丈なのと柔なのと。そしてCDや文庫、A4などの規格サイズが収まりやすいサイズの段ボールかも要チェック。
2)収納ノートをつける。特に我が家の箱好きというか、箱を取っておいていざというときに使おうと考える体質の者が多い家では、それをしっかり書き留めておかないと「いざというとき」が絶対に「いざというとき」にならない。特に箱のなかに箱を入れている場合はその階層までしっかり書き留めるべし。
3)これは引越屋への注文ですが、段ボールを閉じる用のガムテープってアレ、色分けしたものを用意する気はないのかね? それがあれば、各部屋の名前を書いておかなくてもこの部屋はこの色みたいな感じで仕分けできる。たいてい引越屋が準備する段ボール箱って側面に品名・設置場所等を書く欄が用意されてるけど、引越屋の兄ちゃんの動き見てるといちいち側面確認するの面倒のようだし、依頼側としても設置場所が書いてない段ボールなら次の引越時にも使い回しが利く。各部屋の入口のところにその該当する色のテープを貼っておけば、引越屋にとってもワカリイイと思うんだがなぁ。
床スラブのコンクリート打設



初音すまい研究所@監理報告より
中央の写真はベースパックの部分です。
内部型枠を取り外し、一部補修する為に、打ち残してあります(写真右)。
2004年02月21日 (土)
INAX: サーモフロア
父が毎晩見ているワールドビジネスサテライト(テレビ東京)で、INAX のユニットバスの床が4月から変わるらしいと言って電話してきた。
なんでも浴室の床をランニングコストゼロで暖かくする効果のある新床材が開発され、価格据え置きのまま、2004年4月1日(木)より導入されるんだとか。
そういえばうちのユニットバス最終〆が3月中旬、工事は4月後半ってことになってるんだが、何とかサーモフロアに出来るんでしょか?(^^;)
INAX サイトでもまだニュース記事での掲載状態なんで、追記で概要のみ全コピしときます。
2004年02月19日 (木)
現地ノイズ調査
1Fギャラリー車庫側ガラス戸をどうするかの問題で、実際に現場や近所のコンビニ・薬局に入ってどのくらいのノイズがあるか確かめてみましょうという提案が豊田さんからあり、多少元気になってきている母に出向いてもらった(音の問題はそこでピアノのレッスンをするかもしれない母にとってこそが一番重要なのだ)。
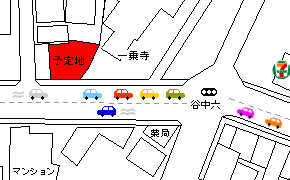 まず向かいの道路は図のように谷中六丁目の信号のところで車が減速するため、うちの敷地にとって手前の車線の方が心持ち車の騒音が少なかったのはラッキーな話であった。しかし、いずれにしても言問通りの車の往来が激しいことに変わりはなく、エンジンを吹かす音などはきっと防ぎようがないにちがいない。
まず向かいの道路は図のように谷中六丁目の信号のところで車が減速するため、うちの敷地にとって手前の車線の方が心持ち車の騒音が少なかったのはラッキーな話であった。しかし、いずれにしても言問通りの車の往来が激しいことに変わりはなく、エンジンを吹かす音などはきっと防ぎようがないにちがいない。
向かいの薬局はまさしく車が加速する箇所に位置するゆえ、店内に入ってもかなりの騒音は感じられたとか。サッシュも昔のものが使われているらしい。それではなかなかうちと比較してという判断はしづらい。
セブンイレブンも同一車線とはいえ、信号の手前と先とでは対比しづらいところではあるが、かなり頑丈なサッシュが入っていて、店内の奥の方にいればほとんど外の騒音は気にならなかったらしい。ただ、逆に店内のBGMがうるさくてそれが判断を曇らせていたところもあったようだ。
その後、セブンイレブンのさらに先の喜久月という和菓子屋にも入ってみたらしいが、そこもサッシュがあまり本格的でないのが使われていて、参考にはならなかったようだ。
さて結論だが、その後に初音すまい研究所で話し合った結果によると、こちらが提案していたスペーシア(※1)の利用は確かに騒音はうるさいがそこまでガラスの質を高めるのはちょっとコスト的に見て勿体ないのでは?という話になったらしい。ガラスの質を高めるということはそれに見合うだけのものにサッシュのレベルもあげないとならないし、加えて光庭側の大きなガラス戸も全体のバランスにあわせてランクをあげていかなければならなくなってしまう。
そもそも最近のサッシュはふつうの一枚ガラスのものでも遮音性能はかなり高いらしく、たとえばエアタイト仕様にしてもしなくても騒音指数はほぼ変わらないらしいのである。あと、これは母が OZONE で聞いてきた話だが、車の騒音という面で見た場合にはペアガラスよりも一枚ガラスの方が遮音性能が高いというのである。それ以外の音の例は母が聞いてきた話だからわからないが、ともかく当初の計画通り、一枚ガラスで一ランク上のサッシュを使い、どうしてもうるさいという場合には後からスペーシアを入れたらどうだろう?というところで話は落ち着いた。
と結局たっぷり打合せといってもいいくらいの話をしてきたみたいで、病み上がりとまで行けてない母ゆえ、帰ってきてからどっと疲れてしまったらしい。なんせ病んでなくても打合せは疲れますからね。おつかれさまです。
−現場、薬局、セブンイレブン、喜久月、初音すまい研究所
−15:00〜18:30
−豊田さん、矢原さん、母
基礎スラブ板



初音すまい研究所@監理報告より
ベースパックの上部は鉄骨架構を組んだ後、コンクリートを打設します(写真中央)。
土留め杭と近接している箇所は、土留め杭の一部を切断し、必要なかぶり厚を確保することにしました(写真右)。
2004年02月17日 (火)
キッチン水栓金具巡り
前夜、母から「TOTO のキッチン水栓金具を実際に見に行ってみたけど、どうもいまいち。っていうか、帰りに GROHE 寄ったらやっぱり GROHE の方がしっかり出来てて、デザインも洗練されてる。値段も TOTO のより安いくらいだし、なんだか GROHE のにしたくなっちゃった。ちょっと大阪のショールーム行って見較べてきてよ〜」というような内容の電話が入る。
こういう電話が入ってきたときにはさっさと見に行っておかないと毎日のように電話がかかってきたりするので、妻を連れ立って行ってくることにした。クリナップのシステムキッチンが3月以降にモデルチェンジですでにショールームでは展示されてるという情報もあったので、TOTO → GROHE → INAX → クリナップとちょっとしたショールーム自転車小旅行である(これまでに5回くらいはやってるんじゃないか?)
 さて、まず最初に行った TOTO のスワン型水栓金具だが、展示品の備え付け方が悪いのかガタガタして、まずそれだけで印象悪〜って感じ。さらには先端部のハンドシャワーになってるところが取り外し装着共にやりづらい。そしてフェイクの宿命とでも言いますか、やっぱ確かに母が言ってるようにデザインがダサいんだよね。
さて、まず最初に行った TOTO のスワン型水栓金具だが、展示品の備え付け方が悪いのかガタガタして、まずそれだけで印象悪〜って感じ。さらには先端部のハンドシャワーになってるところが取り外し装着共にやりづらい。そしてフェイクの宿命とでも言いますか、やっぱ確かに母が言ってるようにデザインがダサいんだよね。
高齢者対応という謳い文句で水栓口のところが工夫されてるって話だったが、妻が何度もそれをひねりながら何だかかえって使いにくいんじゃない?と漏らしていた。そんな否定的感想のなかで母が唯一買っているのがカートリッジの鉛・総トリハロメタン除去機能が他社よりもかなり優れているってこと。しかし、カートリッジ自体が高価なので買い換えていかないとならないことを考えるとやっぱり厳しい。
 続いて行ったのが、ドイツに本社を置く GROHE。
続いて行ったのが、ドイツに本社を置く GROHE。
大阪のショールームはショールームというよりは事務所の一室といった感じだったけど、やっぱり製品そのものはどれを取ってもがっちりしててカッチョエエ。ま、車でいうところのベンツみたいなもんだろうね。
とりあえずスワン型でも GROHE のならば、いくつかの要素は目をつむってもデザインで許せるかな?と思わせるだけのものはある。
ちなみにその目をつむる要素とは蛇口から出てくる水が粒子状の細かい水が出て来はするんだが、シャワー吐水への切り替えができないことである。食器を洗うにはシャワーになった方が断然洗いやすいことを知っているので、その点を聞くと一応アクセサリーとしてシャワー切り替え可能なセラミックカートリッヂが別売りされてはいるが、このスワン型の場合にはちょっとシャワー口が下になりすぎてしまって使いにくいんだとか。つまりシャワーは諦めろ!ってことだが、それでも仕方ないかと思ったのは、今度から食器洗い乾燥機が付くので皿洗いもそんなにしなくなるのかな?と思ったからである(後で母に聞いたら、漆ものは手で洗うとのこと)。値段は¥44,000- で TOTO の¥49,500- より安いからちょっと驚き。取り付け口の口径が34mm〜37mmまで入るということで、クリナップならば問題ない(36mm)ということもあとで確認。
 最後に行ったのが、INAX とクリナップ。
最後に行ったのが、INAX とクリナップ。
共に大きな目的はこの春のモデルチェンジについて。
INAX はバスは変化なし。トイレは4月改変で3月半ばからカタログ&ショールーム展示が始まるとのこと。
クリナップで予定しているキッチン「クリナップ S.S.ステンキャビ」はすでにモデルチェンジしたものがショールームに展示されていて、3月から新機種契約が可能とのこと。
主な変更点として引き出しがこれまで業界最長だった(55cm)のをさらに奥まで伸ばし、60cmという限界ギリギリ(ワークトップの奥行きが65cm)の奥行きに挑戦したという。
シンクに制振層を設けることでこれまでお湯を流したときに起こるステンレスの「ボッコン」という反り返り音を低減。その他にも引き出しレール等で静音効果は高められているらしい。
そしてもう一つ変わったのが、パネルの色。木目柄の2色は前を引き継いだが、単色系がなくなってワッフル地をモチーフとしたホワイト、イエロー、ブルーが新規に設定された。近くで見るとそのワッフル柄がかなりダサい。私はもともと木目柄のフローパインナチュラル(W3)が良いと思っていたので、とりあえずそれがなくならずよかったが、妻は途中からそのダサいワッフルも案外悪くないかも?と言い出していた。さて、どの色となるのでしょう???
クリナップにはスワン型の水栓金具はなく、当初装着予定の金具がお試しで水も出せるようになってたので試してみると、いくら GROHE が良いとはいってもやっぱりこれが一番無難なんじゃないか?と思えてしまった。
2004年02月15日 (日)
ヤキバノカエリ
 NHKの新日曜美術館で熊谷守一(※1)の特集をやっていたのだが、「ヤキバノカエリ」という云わば彼の転機となった作品(熊谷スタイルとでもいうべきものが築かれた)を見ていて、ふと、このサイトと色調が似てるなと思った。ま、あくまで偶然ではあるが、下の comments (0) ってとこをクリックすればフォームの入力欄は白である(笑)
NHKの新日曜美術館で熊谷守一(※1)の特集をやっていたのだが、「ヤキバノカエリ」という云わば彼の転機となった作品(熊谷スタイルとでもいうべきものが築かれた)を見ていて、ふと、このサイトと色調が似てるなと思った。ま、あくまで偶然ではあるが、下の comments (0) ってとこをクリックすればフォームの入力欄は白である(笑)
ま、肝心の境界線の赤はないのだけれど。。そういえば我が家の壁にほとんど壁と同化しかけた感じで貼ってあるブラックのポスター(※2)にいるブラックお得意の鳥が白いのだが、遺骨の白と同じように見えてしまう。そうやって改めて見返すと、あの鳥と遺骨はいったいどっちが生きててどっちが死んでいるんだろう? 見れば見るほど頭が混乱してきてしまった。
有楽町線で池袋の一つ先の要町という駅に熊谷作品のサイズにふさわしい大きさの熊谷守一美術館があるので、もう一度見ておいてもいいかもしれない。
なお、現在『熊谷守一展──超俗の画人、いのちのかたち』が名古屋、京都、大阪、静岡と巡回中(東京、やらないのね)で先月、名古屋に行った折にJR名古屋高島屋で母と見てしまったのだが、疲弊しきった状態で見ているので、3/31〜4/12の大阪展(なんば高島屋)を見逃さないようにせねば!である。
TOTO: 洗濯機用水栓金具
 同じく水栓金具に関して、こちらは FAX で届いた。
同じく水栓金具に関して、こちらは FAX で届いた。
洗濯機用水栓金具に TOTO 製のピタットくん(※1)という壁埋込式の商品を見つけたということで、確かにこれならばふつうの金属系蛇口型のを持ってくるよりも洗濯機の上がすっきりしそうな感じではある。特にうちの場合、将来的に予定されているドラム式洗濯機のサイズが未定であるゆえに。
ただ、混合栓にするか単水栓にするかで節約家族の我が家を気にしてか、母も風呂の湯を使うからいいか〜とは言っていたが、本音は混合栓にしたいんだろうな。価格はちょうど倍。ま、我々の代になったら間違いなく温水は使われなくなってしまうだろうが。。
TOTO: キッチン水栓金具
母からキッチン用水栓金具のことで電話。
声がだいぶ元に戻ってきてるので、聞いてみると声帯炎の方は治ってきてるけど、体調自体はまだいまいちなんだとか。しかし、声が出るようになって途端に電話の本数が増えたような気がする(笑)
 さて、用件だが、予定のシステムキッチン(クリナップ S.S.ステンキャビ)一式の、水洗金具の部分だけ TOTO製のシングルレバー混合栓に変えたいらしい。おそらく母が望んでいるのはこのページの下の方に出てくる右写真の以下商品である。
さて、用件だが、予定のシステムキッチン(クリナップ S.S.ステンキャビ)一式の、水洗金具の部分だけ TOTO製のシングルレバー混合栓に変えたいらしい。おそらく母が望んでいるのはこのページの下の方に出てくる右写真の以下商品である。
品番:TKN34PB(ハンドシャワー、ソフト、シャワー切替)
希望小売価格:49,500円
どうも母はこういう柄の部分が丸くなったスワン型の洒落たのがお好みらしい。
本当は GROHE のにしたいみたいなんだが、高額なのとメンテや万一搬入時に不備があったときの交換に輸入物は時間を取られる心配があるんで、本人も諦めざるを得なかったのである。
しかし、TOTO ならばその理由も該当せず、材料費自体も4〜5000円上回るだけ。ま、工事費が別口となって人件費で一気に上乗せの可能性もあるが、一応豊田さんには直接連絡するよう話した。
2004年02月13日 (金)
基礎地中梁の型枠作り


初音すまい研究所@監理報告より
型枠の中のゴミが幾つか入ってしまっていたので、取り除いた後コンクリートを打設するよう指示しました(写真右)。
2004年02月10日 (火)
ガス&水道メーターの設置位置
給排水衛生計画上のことで豊田さんから電話。
これまで西隣の家とうちとの間にできる通路下に、配水管、そしてその下に給水管+ガス管を引く計画だったが、メンテナンスのことを考えるとすべてを一つところに配管してしまうのはちょっときついかも?という指摘を設備側から受けたとのこと。
その回避策として、一乗寺側に給水管+ガス管を回すことが考えられるのだが、そうすると問題となるのがガスメーターと水道メーターの設置位置。現状では玄関右手の倉庫の中が望ましいが、25cm角×1m くらいメーターのためのスペースを取らなければならなくなってしまう。
私の回答はやむを得ないでしょうってことだが、実家の方はどう考えるのか。
ちょっと説明が難しそうだったので、豊田さんに実家の方にも直接問い合わせの電話を入れてもらった。
トステムのカタログ請求
 サッシの色味情報等を改めて確認したくて、トステムのカタログ請求をしたのだが、想像を遙かに超える量のカタログ類が届いてしまって、ちょっと焦ってます。
サッシの色味情報等を改めて確認したくて、トステムのカタログ請求をしたのだが、想像を遙かに超える量のカタログ類が届いてしまって、ちょっと焦ってます。
カタログ請求のフォームページを改めてよく見ると商品別カタログセットには冊数がしっかり併記されてて、ちゃんと確認してから請求すべきだった(^^;)
参考までにどれをチェックしたらこれだけの量になったか追記しときます。
2004年02月07日 (土)
フッコーの吹付材
 株式会社フッコーの大阪営業所にメールで請求したALCパネルへの吹付材のサンプルが届いた。
株式会社フッコーの大阪営業所にメールで請求したALCパネルへの吹付材のサンプルが届いた。
請求したのは「FMX(吹付)キャンバス FMX-101〜110、116」と先日初音すまい研究所で見せてもらったものにプラス何色か加えてみた。
しかし、これらサンプルは並べて見るのと単体で見るのだけでも印象が異なるように、実際に建物に使われたときのイメージを想定するのは非常に難しい。
初音すまい研究所で玄関〜パーゴラ位置に使われるガルバリウム+杉縁甲板+吹付材の組み合わせを見たときには FMX-101 が一番スッキリした組み合わせとなる印象を受けたが、単体で見た場合には FMX-103 の方が好ましい色に見えてしまう(それは父も妻も同様)。
ただ、ここでは組み合わせから生まれる色合いの方が重要なわけで、そういう意味では FMX-101 となっていく可能性が高そうだ。
2004年02月04日 (水)
blog スタイル色
実はこの blog 本体のサイトカラーは豊田さんが最初に提示された黄色ベースの外観色に合わせてってことだったんだけど、白ベースの黒サッシという風に思いっきし変わってしまいました。
で、まあ、いまさら変更するのも面倒なんで、これはこれでこのまま行きます。
妻からは挽き茶の羊羹みたいと言われておりますが(^^;)
2004年02月03日 (火)
アランさんのアトリエ訪問
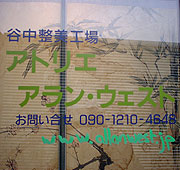 節分の豆撒きに出掛けていたアランさん(※1)の帰りを待って、17時過ぎにアトリエを訪問。
節分の豆撒きに出掛けていたアランさん(※1)の帰りを待って、17時過ぎにアトリエを訪問。
アランさんの展示スペースを兼ねたアトリエが、うちよりも一回り大きいくらいなこと、また彼が日本画家であることなどから照明のことを中心にいろいろ伺った。アランさんのアトリエは元々自動車整備工場だったところを改装して作られているせいで、当然工場の趣を残しているが、もう何年も前から倉庫や工場跡を展示空間にした企画など当たり前になっているので、父でさえそうした空間に違和感はない。ただ、アランさんご本人が雨漏りが多くて困るとは漏らされていたが。。
床には畳地の茣蓙が畳状に敷いてあり、一見すると柔道場のようでもある。去年の art-Link のときのイベントで舞踊の先生に踊ってもらうということで敷いたらしいのだが、それ以降、その畳地の暖かさが気に入ってしまって外す気がなくなってしまったのだという。畳を敷いていると不思議と人を招きやすくなるんだとか。それと訪れる人の滞在時間が自ずと延びるらしい。うちもギャラリースペースを靴脱ぎにするかしないかで一時意見が分かれたが、とりあえず靴脱ぎで始めるという考えは間違っていないと思う。チャレンジする価値だけでもある。
照明に関しては工場の名残で付いてるらしき蛍光灯は一切使わず、ほとんどスポットの光だけで屏風や軸を照らされている。本当はUVカットのものを使った方がいいんだけどと言われながら、そうではない小ぶりのスポットを複数使って光を散らされていた。スポットを付けるためのレールの位置が案外難しいとのこと。屏風が大きいからといって離れたところに付けても、人が絵に近寄って見ようとしたときに影が出来てしまう。ただ、基本的に屏風はどんなところであれ、大抵はその場所に馴染んでしまうんだとか、、もともと屏風は室内に立てて風を避けたり、パーテション的役割を果たしていた建具の延長上のものなのである。しかし、その代わりと言ってはなんだが、掛け軸の飾る場所というのが難しいんだとか。元々は床の間に掛けられるものとしてあった訳だが、それを西洋的な展示壁に設置しようとするとどうしても違和感が残る。また、そばを人が通ると風で捲り上がりやすくなるという欠点もある。そういう意味で結局、柱と柱の間とか、どことなく床の間的空間に置くのが一番すっきりするというのが現時点での結論らしい。確かにうちでも軸の設置位置には難儀しそうだ。思えば三鷹市美術ギャラリーやトウキョウ・マリンギャラリーでの展示時にも自ずと軸はコの字型に囲われたところに展示していた。
照明に話を戻すと、アランさんはいつも秋葉原と上野広小路の間あたりの光東電気(※2)という特殊電球店でスポットを購入されてるとのこと。このお店はスポットの照り具合とかいろいろ確認させてくれて非常に親切に店員が対応してくれるんだとか。また、値段もお安いとのこと。
そういえば日本画の顔料である岩絵具は良いモノを使っていると変質しにくく(昔のものなら大抵良いモノが使われている)、そういう意味では絹本や紙本に地の塗り残しを多く取っている作品は逆にその岩絵具の載ってないところが傷みやすいんだとか。言われてみれば、確かに先月愛知の今枝邸から出て来た芥子の作品の傷んでる部分はまさしくその地の部分であった。
第18回打合せ: ファサードの色調
第18回打合せのところでも書いたようにまず今回の打合せの席で豊田さんからこれまでの黄色ベースの暖かいイメージから白ベースで黒サッシというちょっと緊張感のある色調に建物のイメージをがらりと変えたいという意向があることを伝えられる。
 実は豊田案の図面と模型を初めて見せられたとき、まあ、模型がスチレン色で白かったせいもあるかもしれないけど、漠然とこの形なら色のこと深く考えなくても充分イケる!つまり白で持ってってもしっかり個性の発揮できる器になるだろうという安堵感が第一印象としてあった(大袈裟に言えば肩の荷が下りたような気分にさえなったものだ)。
実は豊田案の図面と模型を初めて見せられたとき、まあ、模型がスチレン色で白かったせいもあるかもしれないけど、漠然とこの形なら色のこと深く考えなくても充分イケる!つまり白で持ってってもしっかり個性の発揮できる器になるだろうという安堵感が第一印象としてあった(大袈裟に言えば肩の荷が下りたような気分にさえなったものだ)。
しかし、先月、豊田さんから黄色で塗り絵した図面を見せられたりして、無難に白に落とさないで考えて行くのもそれはそれで面白い考え方だと成り行きを見まもっていた(黄色はキスケの色だから好きだしね)のだが、実際問題、予定している吹付材のサンプル色に満足できそうな黄色系統色が見つからなかったのと、あったとしても一乗寺の隣という立地で暖色系の家が建つと少し場違いにほのぼのしすぎるのではないか?(田園みたいなところにぽつんと佇む家ならいいけれど)と思われるようにもなったらしく、そのときサンプルで取り寄せていたほんのり蒼味掛かった白色(フッコー FMX-101)をベースにする方向に考え直されたらしい。
吹付材の色見本を現場に持って行って、エントランス軒下に張る杉縁甲板やガルバリウム鋼板の色と組み合わせて見ていくと、確かにその白(FMX-101)がスキッとした透明度を持っており、単純に風景に馴染むというよりは、それら3色が微妙な緊張度で干渉し合いながらもふわっと浮き上がる感じでちょっと不可思議な印象を与える。父はサンプルを単体で見ていた当初はそれより少しクリーム色掛かった白(FMX-103)を好んでいたが、組み合わせると FMX-101 の方がよいと豊田さんの考えに賛同。私もほぼ同意見。帰宅後、経緯報告してから判断を仰いだ母も同意見だったが、どうせなら何の説明もなしにどれが好みか聞いてみるんだった。
 事務所に戻ってからエントランス部のみの 1:10 の模型を見せてもらう。
事務所に戻ってからエントランス部のみの 1:10 の模型を見せてもらう。
先の3色に、さらに黒い玄関扉と搬入口のサッシの色が入ってくるとまただいぶ印象が違う。FMX-101 の色味が単純に白とは言い難い色をしているので、スチレン色と組み合わさった黒色では逆にイメージが捉えにくい。それとパーゴラの檜も紙でできてるので、これが木の色だったらばまただいぶ印象も違っただろう。
それから玄関ドアをこの模型のように重たく黒でどっしりさせた場合、取っ手部分は考えようによってはデザイナーに発注するような、すこし変わったものを持ってきて、アクセントを持たせてもいいのではないか?とのこと。まあ、確かに黒でずっしりだけだとちょっと人を寄せ付けない入口になってしまうかもしれない。しかし、こういう話の流れになってくると途端に「じゃ、取っ手だけDIYしたいです!」というセリフが喉元から出掛かってしまう。何とか自制したが、もしそれが木でもOKなら、総領の義父と作りたいものだ。
豊田さんとしては1920年代の近代建築的イメージになってきてしまったかも?と、具体例としてル・コルビュジエのシュタイン邸を挙げておられた。
第1回現場見学
 臨時打合せ翌日の工事見学を除くと地鎮祭が行われてからの公式的な現場見学は今回が1回目となる。現場は小雨がぱらついて予定されていた配筋調整の工事も小休止の様子。
臨時打合せ翌日の工事見学を除くと地鎮祭が行われてからの公式的な現場見学は今回が1回目となる。現場は小雨がぱらついて予定されていた配筋調整の工事も小休止の様子。
豊田さんからは配筋調整の必要な箇所の説明、また配筋されて朧気ながら見えてきた建物のスケール感(結構大きいですよと言われて父は首を傾げていたが)の話など聞く。
正直、現在の私はこのスケールに対して大きいか小さいかの判断は持てない。とりあえず現場では約1ヶ月弱お預けとなっていた敷地の、というか工事過程の一場面をデジカメの静止画+動画で撮りまくった。
上棟式の日取り
上棟式(※1)の日取りを豊田さんはしっかり足場の整う3月半ばあたりで望まれていたが(その方が我々が実地に立っていろいろイメージを膨らませやすいため)、山本さんからはその時期に現場に踏み込まれると工事進行上妨げになりかねないというお話。そこで波板型の鉄板床が入った直後ならということで、3/6(土)の大安日になった。ちなみに父は高所恐怖症で、棟にあがるのは遠慮するんだとか(父の高所恐怖症話、初めて聞きました)。
上棟式には鳶職人と鉄骨屋さんが参加。お祝儀として職人さんたちにそれぞれ1万ずつ、親方は2万というのが東京の相場らしい。地方に行くとそれが半分くらいになる様子。それ以外に準備するものとしては、お酒(一合瓶×人数分)、赤飯、千円前後の弁当もしくはお菓子(最近はお菓子が多いとのこと)で、お酒と赤飯は阿部さんがいつも頼んでいるところにお任せすることもできるらしい。
職人のみなさんはほとんど車で来ているので、実際にお酒を飲むことはできない。よって昔のように車座になってわいわいがやがや酔いしれるといった祝祭的イメージはおそらくない。たぶん乾杯で一口つけるだけになるだろう。
母が三隣亡(※2)の日に上棟式を行うのだけはやめてほしいと言っていたが、打合せ時にはそれを確認する術がなく、大安だからといって日柄に特に関心のない男たちだけで決めてしまった 3/6(土)は運良くその日を免れていた。
なお、山本さんから棟飾(※3)はつけますという話もあった。三鷹金猊居を解体するときに玄関屋根裏から加藤という棟梁の名の刻まれた棟飾が出て来ているのを見ているだけに、その申し出は素直に嬉しい。日柄とか気にする方ではないが、金猊居にあった幾つかの習わしは引き継ぎたいものである。しかし、鉄骨建築の場合、どこに飾るんでしょうね〜?(笑)
第18回打合せ: 白い家
 工事が本格始動してからは毎週火曜に行われている定例会に併せ、打合せも月1ペースで火曜に行うこととなったのだが、先月末あたりから母が声帯炎を患い、当初予定の1/27(火)から1週遅らせても快復しなかったのでこの日に行うこととなった。
工事が本格始動してからは毎週火曜に行われている定例会に併せ、打合せも月1ペースで火曜に行うこととなったのだが、先月末あたりから母が声帯炎を患い、当初予定の1/27(火)から1週遅らせても快復しなかったのでこの日に行うこととなった。
主な打合せ内容は工事状況の説明(※1)、今後のスケジュール(※2)、検案・検討事項の確認(※3)、母からの質問(※4)といったところだが、大きな変化としては先月提示されたファサードの色彩イメージががらりと変わったということが第一にあげられる。
黄色ベースだったのが、白ベースに黒サッシという具合に豊田さんの考え方は移行してました。
取り寄せた吹付サンプルを見せてもらったり、現場にサンプルを持ち込んでエントランス軒下に張る杉縁甲板やガルバリウム鋼板の色とも組み合わせて考えてみたり。ファサードの色彩イメージについては別稿にて。
また、近所にアトリエを構える日本画家のアラン・ウェストさん宅を訪問し、照明についてのアドバイスをいろいろ伺ったけど、それに関しても別稿にて。
−初音すまい研究所、現場、アランさんのアトリエ
−14:00〜20:00
−山本さん、豊田さん、矢原さん、父、私(+ゲスト:アランさん)
−契約書、意匠・設備図面、構造図面(以上、綴じ本)、管理報告ファイル、工事工程計画表、打合せ記録
=トイレットペーパーホルダー、タオルかけ、MO
 うちの敷地から東南東に5、60mくらいのところに位置する界隈唯一の大型マンション(14階建て)。
うちの敷地から東南東に5、60mくらいのところに位置する界隈唯一の大型マンション(14階建て)。 こうした運動は以前私が住んでいた京都でもよく目にしていたので、谷中で土地探しをしていた時分、マンション前に張られた横断幕を見て、懐かしくといっては語弊があるが、京ライフを思い起こしたものだ。
こうした運動は以前私が住んでいた京都でもよく目にしていたので、谷中で土地探しをしていた時分、マンション前に張られた横断幕を見て、懐かしくといっては語弊があるが、京ライフを思い起こしたものだ。 初音すまい研究所@監理報告より
初音すまい研究所@監理報告より
