しかし、そんな早熟多才な祖父が私の目から見て決して満足な一生を送れなかったように思える理由の一つにこの三鷹金猊居の存在があるような気がしてならない。1997年10月に祖父の遺作展(※1)を企画した私はその挨拶文で「不遇」という言葉を使ったが、今回の家作りという経験はその言葉の採用に些かの疑問を抱くものとなった。私は9歳のときに祖父を亡くして以降、母方の身内からは事あるごとに祖父は無念を残したまま死んでしまった、時代が悪かったという話を聞かされてきたが、果たしてその話を鵜呑みにしていて良いのだろうかと思い始めたのである。
「不遇」という言葉には運や巡り合わせといった自力ではどうにもならない不可抗力が働いてしまったからこそ陥ってしまった不幸な境遇といったニュアンスがある。確かに祖父の場合は「時代が悪かった」という言葉が示す通り、人生これからというときに太平洋戦争を迎え、また両親に弟の戦死と相次ぐ身内の不幸にも翻弄された──そんな話を聞かされれば迷うことなく「不遇」という言葉をあてがいたくなってしまうものだが、どうだろう? もし祖父がそうした人生の分岐点ともいうべき時期に自身の家を構えていなかったとしたら? 家作りという大事業に身を投じることなく画業に専念していたとしたら?──もちろんこの疑問に答えを出すことはできない。だが、祖父の履歴書は自邸の完成以前以後であまりにも歴然とその明暗が分かれているのである。即ちそれは祖父が人生の岐路において致命的な選択ミスをしていたのではないか?(つまりおしなべて「不遇」とは言い切れないのではないか?)ということだ。
 ここで結論を出す前に祖父が家を建てた時期のことを再検証しておきたい。
ここで結論を出す前に祖父が家を建てた時期のことを再検証しておきたい。
三鷹金猊居は資料に拠れば1939(昭和14)年、即ち日独伊三国同盟が成立する前年、第二次世界大戦が勃発せんというときに建てられている。その2年前の27歳で祖父は結婚しているので、年齢的には早いような気もするが、結婚を機に一家の主として居を構えたくなったというのは当時においても自然な流れと言えるだろう。
だが、ここで当時の時代背景の方に目を傾けると、何て不安定な時期にそれも東京の三鷹という充分戦火の及びそうな地域に家を建ててしまったのか?という声が聞こえてきそうである。だが、それは歴史を後から見た者の視点であり、実は北朝鮮のテポドンがいつ飛んで来るか知れぬのにそのことにさほどリアリティを持てずにいる現在の我々と似たような状況なのかもしれない。つまり築造当時、東京が戦場になることなど多くの国民は考えもしなかったのではないか。とすれば、その時代性において祖父が家を建てる時期を見誤ったとは一概には言いづらくなってくる。
むしろ私が疑いを掛けたいのは当時の祖父の内面の方にある。さきほど私は結婚→新築を自然な流れとしたが、それはあくまで当時にあって完全に自立した一般成人のことを差しているのであって、祖父にもそれが該当するとは実は考えていない。家作りの経緯については長女である母でさえ家が完成して5年後に生まれているので、例えばどのような資金繰りが行われたのかとかいう実情を子供心に見ることもできなければ、ちゃんとした話としても聞かされてもいない。だから想像でしかモノが言えないのだが、少なくとも私の目から見て、日本画家だった祖父が自力で家を建てたとは到底思えないのである。ましてや東京という土地でありながら広大な敷地に精巧極まる建具意匠と、とても標準的な家のスケールでは収まり切らぬ、言ってしまえば屋敷に近い家を建ててしまうことが出来たのには、祖父母両実家およびその周辺親族の財力(援助)あっての話と思わざるを得ない。
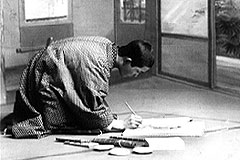 これも推測に過ぎないのだが、おそらく祖父は祖母と結婚したことで、その虚栄心から三鷹金猊居をあのような若さで建ててしまったのではないか?──それが私が今回の家作りを通して辿り着いた祖父の「不遇」という境遇に対する新たな見方であった。即ち祖父は不遇な境遇から自分の人生を貧しくしたのではなく、自らの虚栄心によって人生のバッドカードを引いてしまったのではないか?ということだ。それは何だかんだ言いつつ30代前半で自分がすぐに住むという訳ではないものの、施主責任者として2年掛かりで家作りに没頭していた私自身にも微妙に重なっている。
これも推測に過ぎないのだが、おそらく祖父は祖母と結婚したことで、その虚栄心から三鷹金猊居をあのような若さで建ててしまったのではないか?──それが私が今回の家作りを通して辿り着いた祖父の「不遇」という境遇に対する新たな見方であった。即ち祖父は不遇な境遇から自分の人生を貧しくしたのではなく、自らの虚栄心によって人生のバッドカードを引いてしまったのではないか?ということだ。それは何だかんだ言いつつ30代前半で自分がすぐに住むという訳ではないものの、施主責任者として2年掛かりで家作りに没頭していた私自身にも微妙に重なっている。
少なくとも祖父は自分がアーティストだという自覚で生きていこうとする限り、そんな歳で家を持つ必要などまったくなかったはずだ。大作を描くためのアトリエが欲しかったということもあるのかもしれないが、まともなアトリエを持たずに大成した画家など幾らでもいる。むしろ画家と貧乏はいつの時代も背中合わせのものであり、アトリエ持つのも家を構えるのも、それらは本人の納得行く成果が得られてからでも遅くはなかったのではないだろうか。良くも悪くも家を建てるということはその人間の自由を束縛するものなのだから。
*
以上、これはほんの一握りしかいないアーティストという職種の特殊事例とも言えるが、自分の家を建てる時期というものが人生に及ぼす影響という意味では、どんな職種の人間にとってもそのタイミング(適齢期)の重要性は変わらないだろう。
住宅ローンの金利が変わるとか、住宅減税、消費税といった類の利率が変わるといったことから住宅購入を急かせようとする業者はたくさんおり、漠然と家を建てたいと思っている者にとっては仮に1%でも額が額だけについ心を揺さぶられがちになるのはやむを得ない心情だろう(言うまでもなく営業担当者はそこを突いてくる)。実際、我が家でも税金控除を目当てに最初の建築家に設計期間の短縮を迫ったことはあった(まあ、最初がのろのろしすぎてたとも言えるのだけど)。だが、そうした焦りから来る切迫は失敗に結びつきやすいものであり、事実それによる失敗を経験した現在、まあ、自分自身が今後自分のために家を建てるということは全く考えられないけど、もしそれがあるとするならば、それは自分を含めた家族が家を持つということに当たって完全に機が熟したと感じられるようになってからで充分なような気はしている。タイミングを誤った人生はなかなか取り返しが利かないが、利息分のお金というものは節約しながら働けば何とかなるものである。住環境を半ばゼロから再整備するに等しい家作りは、社会における自身の力量がおおよそ見え始めるだろう(それは自ずと自身の晩年が朧気ながら見渡せるようになるときであろう)人生の折り返し地点あたりがその適齢期ではないか?というのが私の現時点での持論である。
*

最後にもう一度祖父の話に戻るが、私の中では今回こうした結論を出しておきながら、他方で祖父は画業で満足な結果が残せなくても、実は愛する妻との暮らしを心ゆくまで楽しんでおり、まわりが言うほどには不幸な人生でもなかったのではないか?とも考えていることを追記しておきたい。まあ、それを言ってしまうとここまで書いてきた話がすべて身も蓋もなくなってしまうのだが、ある種の諦めの境地の上に成立する(余生?)しかしながら幸せな生活ってどうなんだろう?ってことを34歳の人間が言うべきじゃないんだろうけど、私もまたすでに家を建ててしまってるだけに自らに引き寄せて考えたくなったりもするのだ(汗)
祖父の遺作展で作成したリーフレットには、晩年の祖父が祖母に宛てて書いた手紙が掲載されている。もちろん祖父の許可なんてものはある訳なく、というよりもその過激な内容のため、身内の検閲(顰蹙)を半ば無視する形で私が強引に載せてしまったのだが、その手紙を読んでいると人生の敗北を語りながらもどう見ても不幸というよりは幸福にしか見えない夫婦像が浮かび上がってくるのである。
どこかにテキストデータは残ってるはずなので、見つけたらここでもアップしちゃおっかな〜と(笑)
□◇
≪ 閉じる

 ここで結論を出す前に祖父が家を建てた時期のことを再検証しておきたい。
ここで結論を出す前に祖父が家を建てた時期のことを再検証しておきたい。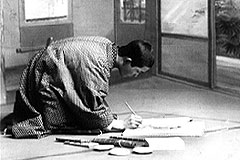 これも推測に過ぎないのだが、おそらく祖父は祖母と結婚したことで、その虚栄心から三鷹金猊居をあのような若さで建ててしまったのではないか?──それが私が今回の家作りを通して辿り着いた祖父の「不遇」という境遇に対する新たな見方であった。即ち祖父は不遇な境遇から自分の人生を貧しくしたのではなく、自らの虚栄心によって人生のバッドカードを引いてしまったのではないか?ということだ。それは何だかんだ言いつつ30代前半で自分がすぐに住むという訳ではないものの、施主責任者として2年掛かりで家作りに没頭していた私自身にも微妙に重なっている。
これも推測に過ぎないのだが、おそらく祖父は祖母と結婚したことで、その虚栄心から三鷹金猊居をあのような若さで建ててしまったのではないか?──それが私が今回の家作りを通して辿り着いた祖父の「不遇」という境遇に対する新たな見方であった。即ち祖父は不遇な境遇から自分の人生を貧しくしたのではなく、自らの虚栄心によって人生のバッドカードを引いてしまったのではないか?ということだ。それは何だかんだ言いつつ30代前半で自分がすぐに住むという訳ではないものの、施主責任者として2年掛かりで家作りに没頭していた私自身にも微妙に重なっている。 最後にもう一度祖父の話に戻るが、私の中では今回こうした結論を出しておきながら、他方で祖父は画業で満足な結果が残せなくても、実は愛する妻との暮らしを心ゆくまで楽しんでおり、まわりが言うほどには不幸な人生でもなかったのではないか?とも考えていることを追記しておきたい。まあ、それを言ってしまうとここまで書いてきた話がすべて身も蓋もなくなってしまうのだが、ある種の諦めの境地の上に成立する(余生?)しかしながら幸せな生活ってどうなんだろう?ってことを34歳の人間が言うべきじゃないんだろうけど、私もまたすでに家を建ててしまってるだけに自らに引き寄せて考えたくなったりもするのだ(汗)
最後にもう一度祖父の話に戻るが、私の中では今回こうした結論を出しておきながら、他方で祖父は画業で満足な結果が残せなくても、実は愛する妻との暮らしを心ゆくまで楽しんでおり、まわりが言うほどには不幸な人生でもなかったのではないか?とも考えていることを追記しておきたい。まあ、それを言ってしまうとここまで書いてきた話がすべて身も蓋もなくなってしまうのだが、ある種の諦めの境地の上に成立する(余生?)しかしながら幸せな生活ってどうなんだろう?ってことを34歳の人間が言うべきじゃないんだろうけど、私もまたすでに家を建ててしまってるだけに自らに引き寄せて考えたくなったりもするのだ(汗)