2004年09月22日 (水)

光庭考: アートネイチャー(※) のエントリー時に「小林古径」で検索かけたら小林古径邸の情報が出て来たので、重ねてエントリーしておきたい。
小林古径邸は「建築家・吉田五十八が設計し、棟梁・岡村仁三が施工した木造二階建・数寄屋造りの住宅」。1993年までは東京都大田区馬込にあったらしいのだが、築後約60年で惜しまれつつ解体。その解体部材を上越市が買い取り、 新潟県上越市本城町の高田公園内で復原工事に着手し、2001年春に完成したとのこと。
詳しくは上越市サイト内の小林古径邸のページに任せるが、どうやら移築後は入館ばかりかアトリエ利用までが可能となっているようだ。素晴らしい!
復原事業のあゆみなどを見ていると羨ましくなってしまう。
ちなみに祖父・金猊の古径から受けた影響は非常に大きい。
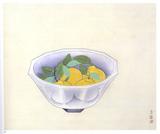 追記欄にて引用される西澤文隆(※) と小林古径(日本画家)による2つの文は共に<自然>と対峙したときに求められる技巧について触れているので、ここに並置しておきたいと思う。
追記欄にて引用される西澤文隆(※) と小林古径(日本画家)による2つの文は共に<自然>と対峙したときに求められる技巧について触れているので、ここに並置しておきたいと思う。
ジャンルこそ異なれ、ここに共通するのは<現実>というフレームに絶えず意識を働かせる視線である。そのフレームは常に<時制>によって脅かされているゆえ、決して形式として固定することが許されず、すなわちその都度違う解決法(=応用力)が求められる。
光庭において縮景・残山剰水といったレベルでの作庭を考えているわけではないが、ただ自然のままにというのではなく、誇張やデフォルメといった要素も取り込んだ庭づくりを楽しんでみたい。
右上の図版は
小林古径【三宝柑】1939年 絹本彩色・軸 60.0×72.0cm 山種美術館蔵
□◇
『西澤文隆の仕事──2. すまう』(P.59) より
日本における木の扱いは、これとまったく異なる。木は、自然のままの姿で使われる。もちろん庭園においては、ことに日本のように室内との関わり合いをもち、ことに室内の延長として意識される場合において、自然は馴化されていなければならない。したがってある程度の剪定が行われ、自然はより自然らしく、やさしく飼い馴らされる。しかし、これはあくまで自然を人工化するのとはおよそ異なる方向である。木は、ヨーロッパにおけるように幾何学的に配置されることなく、さも自然の植生のあるべき姿のように、三々五々、バランスを取りながら植え込まれる。木は1本独立させて使われることはほとんどない。互いに相寄り、相助け合いながら配置されるだけではなく、木は互いに透けていて枝の下に見通しがあり、奥へ奥へと、さも自然植生の姿であるかのごとく、すなわちエコロジカルな様相に植え込まれる。木には添え木があり、さらに下木や下草があって、自然な雰囲気に近いほど、しっとりとよい庭であるとされる。もちろん、先にのべた通り、庭はあくまで庭であって、自然そのものではない。第一、スケールが庭と自然とでは根本的に異なる。その狭いスケールの中でいかに自然らしい庭をつくり出すかが日本庭園のデザインのポイントであるとすれば、そのスケールに合わせて、自然を不自然さを感じさせずに縮小化する必要を生じる。このようにして、縮景と残山剰水の技法が生まれてくる。
東京国立近代美術館企画展図録『写実の系譜 IV:「絵画」の成熟』(P.16) より
ここにあるこの盆一つにしても、ぢつと見てゐると生きてゐる気がする。叩けば音がするし盆には盆の生命があることがわかるのだ。ところが、それを絵にすると、なかなか音がしない。音のする盆をかくのは大変だ。写実といふものも、そこまで行かなければ本当の写実ではない。
ところで、音のするやうな盆をかくのに、真ツ正面からかいてももちろんいゝが、さうするよりも、そのまゝを写さないで、選であらはしたり、また色をなくしてやる方が、よくあらはれる場合がある。そこにウソも生じてくるし、誇張も必要になつてくるだらう。これも技巧だ。
≪ 閉じる
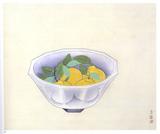 追記欄にて引用される西澤文隆(※) と小林古径(日本画家)による2つの文は共に<自然>と対峙したときに求められる技巧について触れているので、ここに並置しておきたいと思う。
追記欄にて引用される西澤文隆(※) と小林古径(日本画家)による2つの文は共に<自然>と対峙したときに求められる技巧について触れているので、ここに並置しておきたいと思う。